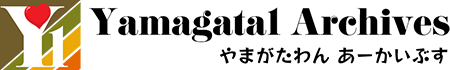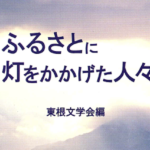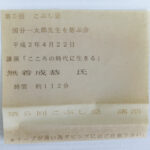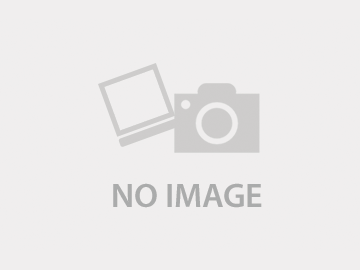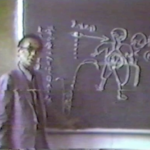AI音声による解説
村川千秋氏と村川 透氏、兄弟お二人が自身の人生、特に音楽と映画の道へと進んだ背景について語るAIの音声です。彼は幼少期の経験、家族からの影響、そして自身の情熱が、どのように彼の芸術的なキャリアを形作っていったのかを詳細に語っています。また、山形県でオーケストラを設立し、地方の音楽文化を育むことへの強い思いや、そのための苦労、そして子供たちの育成の重要性についても触れています。
兄は音楽、弟は映画の道へ(山形交響楽団誕生秘話)
《第1部》子どもたちに生の演奏を
─熱い想いが山形交響楽団の原点─
村川千秋さん(山形市)
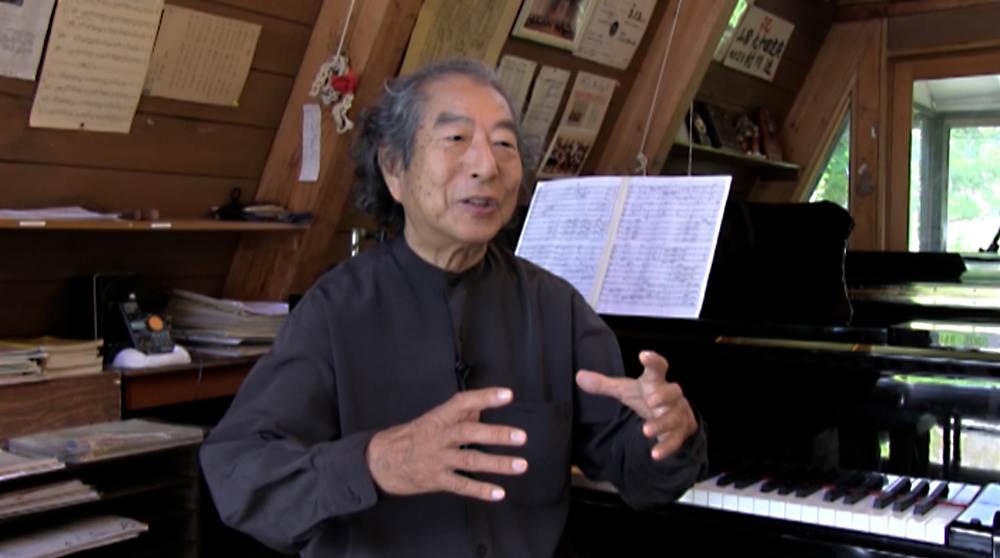
音楽好きは子どもの頃から
私は昭和8年の元旦に村山市で生まれました。
父は今の國學院大学を出た人で楯岡高校の国語の教師、母は専業主婦で、姉と弟が2人いました。
母は優しかったですが、父はすごく厳格な人でした。父に抱っこしてもらったり肩車してもらったりした覚えはありません。長男ということもあって僕には特に厳しく、いつも命令されているようでした。
歌舞伎など日本の芸術文化に造詣が深かった父は、姉に日本舞踊を習わせました。父は僕にも日本舞踊をやらせようとしましたが、言うことを聞かずに音楽のほうにいき、すぐ下の弟は建築の設計、末弟の透は映画と、男兄弟はそれぞれ勝手に自分の好きな道に進みました。後に姉は踊りの師匠になっています。
僕は幼稚園の頃からハーモニカが好きで、何本も壊しては買ってもらうほどいつも吹いていました。それからもずっと音楽は好きでしたが、振り返ってみると山形南高に入り、森山三郎先生と再会したことが本格的に音楽を志すきっかけになったと思います。森山先生は楯岡小学校の3年生の時に音楽を習った先生で、戦地から帰って来て南高の音楽教師をしていたのです。当時は先生と生徒の距離感がすごく近くて、森山先生は合唱、僕は高校生になって器楽に目覚めクラリネットを吹いていましたが、自由な雰囲気の中で一緒に音楽の楽しさを味わいました。それで、ますます音楽が好きになったのです。
山形南高では、後に山形市長を務めた吉村和夫さんが1年先輩で応援団でした。僕は、楽器を集めて同級生に扱い方を教えて吹奏楽部をつくり、彼と組んで母校の応援に熱中しました。
東京芸大へ入り音楽の道へ
東京芸大を目指したのは、高校1年の時です。戦後初めて、東京から山形に来たオーケストラの演奏を聴いて、もうすっかり心を奪われました。それで、演奏が終わるとすぐ楽屋に指揮者の近衛秀麿先生を訪ねていって「音楽やりたいです」と言いました。「何やってるの?」と聞かれたので「クラリネットをやってます」と答えると、「じゃ、来い」と北爪利世先生の楽屋に連れて行ってくれました。そして、東京芸大の先生だった北爪先生に「この子、教えてやれ」と。
それから月に一度、東京まで北爪先生のレッスンに通うようになりました。当時、山形から東京までは汽車で9時間かかりました。夜、山形を出て、朝、東京に着き、夕方までレッスン。また夜の汽車に乗って帰って来て山形に着くのは次の日の朝で、駅からそのまま学校に行くという生活でした。
父は、僕が音楽をやることに大反対でお金をくれなかったので、吹奏楽部の仲間と山形の映画館のアルバイトでチンドン屋をやって稼ぎ、そのお金で東京に行っていました。
ただ、高校生では月謝を払うことまで気が回らず、食糧難の頃だったので御礼に米を持って行ったくらいでしたが、北爪先生も何も言いませんでした。
そうして高校時代はクラリネットに明け暮れ、昭和26年、何とか東京芸大の音楽学部器楽科に入学しました。器楽科の定員は管楽器と打楽器あわせて10人で、当時は地方の高校から合格するのはなかなか難しかったので、自分では本当に〝まぐれ〟で入ったと思っています。
父からは「歌舞音曲は河原乞食がやるもんだ。ダメだ」と言われましたが、僕は「音楽の先生になるんだ」とごまかして東京芸大に行ったのです。その時から音楽の道にはまりました。
東京芸大では器楽科でしたが、2年生の頃から作曲をやりたいと思うようになり、フランス帰りの池内友次郎先生のもとで作曲を習いました。それで器楽科を卒業間際に退学して、作曲科に移ったのです。結局、8年間、東京芸大にいました。
当時は戦後で先生の数が不足していたため、教員の仮免許制度というのがありました。器楽科の3年の時にそれを受けて教員の資格をとり、高校で音楽を教えるようになりました。
生徒が18歳、先生の僕が20歳です。この学生と教員の二足の草鞋は、作曲科を卒業して昭和35年にヤマハに入社するまで続きました。
ヤマハでの仕事はオルガン教室の本部指導講師で、テキストを書き、教室の先生たちに指導法を教えていました。それで、もっと教育法の原理を知りたくなり、インディアナ大学の大学院に留学しました。アメリカの州立大学の音楽学校です。今は日本人の学生も多いですが、あの頃は5人くらいだったでしょうか。チェロの堤剛さんもご一緒でした。僕はもっと教育原理の勉強をしようと思って行ったんですが、ここは現場の学校のコースしかなく、指揮科に入りました。
この時も幸運に恵まれました。ヤマハで書いたテキストを見せると、「大学の助手の採用試験があるので受けろ」と言われ、テストを受けてみたら合格したのです。それで助手になり、大学院生が大学生に教えて給料をもらいながら、ギリギリでしたが何とか勉強を続けることができました。
大学院を卒業する時には、全大学院をあわせて250人くらい卒業生がいましたが、その中で3等賞に選ばれました。
山形に音楽文化を育てることが使命
昭和40年、インディアナ大学を卒業する時に、ある先生から「指揮者のレオポルド・ストコフスキーに紹介してやる」と言われニューヨークに行くことになりました。その頃、ストコフスキーはニューヨークのカーネギーホールでアメリカシンフォニーオーケストラというのをやっていたのです。そこへ紹介してもらうと、ストコフスキーから「すぐ来い」と手紙が来ました。
こうしてストコフスキーのところで学ぶことになりました。一番最初に行った時に「指揮棒を振ってみろ」と言われて手の動き方などを見られましたが、あとはディスカッション。
世界から集まった若い指揮者が10人くらいいて、実際にカーネギーホールでストコフスキーが指揮をするのを見ながら、ディスカッションをするのです。また実際にオーケストラを指揮することもありました。そういうレッスンを1年ほど体験しました。僕は運が良くて、こういう世界の素晴らしい人たちに出会えて本当に幸運だなと思っています。
そのままアメリカで仕事をする道もありましたが、とにかく長男ということで、どうしても日本に帰らなければなりませんでした。ただ、その時、「東京に帰っても指揮をする人は大勢いるから、それでは意味がない」と思ったのです。岩城宏之や小澤征爾は本当に天才ですが、「僕は天才じゃない」という自覚があり、ああいう天才たちと競争して世界を指揮して回っても意味がないと思いました。それよりも、アメリカにいる間ずっと考えていた「田舎に帰ったらオーケストラをつくりたい」という夢を実現しよう、それが僕の仕事だと考えました。
アメリカでは、ロスアンゼルスやヒューストン、テキサス、シアトル、シカゴなど地方都市にもオーケストラがありました。しかし、あの当時、日本では北海道や群馬にはオーケストラがありましたが、東北にはありませんでした。「こんな広い東北に、オーケストラが一つもないのは全くおかしい」と強い憤りを感じて、それで山形に帰って地方の音楽文化を育てなければ…という使命感を持ったのです。
こうしてアメリカ留学から帰国し、「山形県のために東北地方のために交響楽団を設立しましょう」と呼びかけました。「子どもたちに生の演奏を、山形や東北の人たちに本物の音楽を聴かせたい」という一心でした。そして多くの仲間たちの協力を得て、昭和47年に山形交響楽団(山響)を結成、東北地方で初めて、全国では14番目のプロ・オーケストラでした。
子どもたちの素質を伸ばす環境を
山響を立ち上げると、県内の小・中・高校に出かけ、子どもたちの前で演奏する音楽教室をスタートしました。山響を地元のオーケストラとして長く続けていくには、山響を支えてくれる人、聴きに来てくれる人、音楽の好きな人が必要です。山響とそれを支える人は車の両輪で、自分たちの手でそういう人たちをつくっていかなければならない、それには子どもの頃から生の演奏を聴く機会が大事だと考えました。
また当時は、東京と地方では音楽を学ぶ環境に格差がありました。地方には東京のように小・中・高と一貫して音楽を勉強できる学校、一から育ててくれる先生がいるところはありませんでした。今でこそピアノの先生はたくさんいますが、あの頃はピアノ教室の数も少なかったのです。
ですが、東京でも地方でも子どもたちが本来持っている音楽の素質に大きな違いはありません。地方にいても専門的に教えてくれる先生やきちんとした教育システムなどの環境が整っていれば、それを伸ばしてあげられるのです。そうした思いから翌年の昭和48年にヴァイオリン教室「キラキラ会」を立ち上げました。
地方の文化というのは、その土地の人たちが育てようとしない限り誰もやってくれない、自然に育っていくものではないと思います。ですから山形県の人が、子どものうちから文化の芽を育てることを計画的にやっていかないと、絶対に文化は育たないのです。
山形くらいの規模の都道府県で、プロのオーケストラがあるのは群馬と山形だけです。僕は群馬交響楽団の初めの頃、プレーヤーとして演奏したことがあります。そこで「これは素晴らしい、これは山形でも絶対にやらなければ」と思いました。そして「山形でも絶対、やればできる」と強い信念を持って山響をやってきて、もう50年続いています。これは、まさに奇跡だと思っています。
《第2部》兄弟対談
兄は音楽、弟は映画の道へ ─ 父の壁を越えて夢を実現
村川千秋さん・村川透さん

お父さんはどんな方でしたか?
(透)
親父は、とにかく堅物でしたね。国文学者で、戦前の皇国思想というか、神武天皇以来の天皇を崇拝していました。
お客さんが来るとなると、子どもたち全員に「みんな出てこい」と言って、兄貴、姉、それで僕が一番最後のほうに並んで、全員で礼をして「いらっしゃいませ」と迎えたりしましたね。
(千秋)
ご飯の時は、親父とおばあちゃんと女中さんと3人だけ一段上の畳の部屋にいて、僕らは姉と男3人並んで下の板の間にいて、あとお膳が奥までず~っと並んでいました。
(透)
兄貴が一番上で、ず~っとみんなが並んでいて、僕が一番下。お袋の横にいて守られていたけれども、兄貴の千秋のほうは、少しでも何か行儀を崩したり声を出したりすると、親父が下りてきて後ろからいきなりゴーンと。いつも、やられるのは兄貴だけでした。
(千秋)
「ああいうことは、しちゃいけない」という見せしめだったんでしょうね。
(透)
要するに、長男の兄貴は特別、そういう親父でしたね。だから、それを見ていて、「兄貴はかわいそうだな」とは思っていました。「兄貴っていうのは、そういうもんだ」と。
(千秋)
ある時は、悪いことをすると池の中に入れられて、頭を抑えられてズブズブズブ……アップアップって出てくると、また水の中に入れられて。
(透)
そうそう。逃げていくと、親父が向こう側に回って、またこう頭を抑えられて。それを僕は、こっちの渡り廊下のほうで覗いていて「かわいそうだ。兄貴ってあんなにされるんだ」と。でもね、僕にとっては、そこが兄貴の兄貴たるところなわけです。
子ども頃は、何になりたいと思ったのですか?
(透)
お百姓さんになりたいと思ったことがありました。なぜかというと、たとえばお米をつくるだとか、そういうことに朝早くから夜中まで、一心不乱になって働いているお百姓さんに感動したんですよ。
それで僕、朝早くから見に行って、一日中それを観察したことがあるんです。お百姓さんは何かにつけて神様、井戸の神様、家の神様、道具の神様、そういうふうに何でも尊く感じてお米をつくるんですよ。その米がまた、うまい。それで餅をついたりして、みんなに振る舞う。その頃、戦時中でしたから兵隊さんに米を送るんだと。そういう様子を見て、僕はもう「百姓になる」と思いました。
小さい頃にお百姓さんを朝早くから観察していたというのは、やっぱり人間観察がお好きだったのかなと。それで監督の道に進んだのかなという気がしますね。
(透)
そうですね。
(千秋)
僕は、兵隊でした。僕らの時代は、中学に入る時には必ず口頭試問があるから、校長先生に「お前は将来、何になりたいか」と聞かれたら、「はい、特攻隊になります!」と言うんだと先生から教えられて実際にやりましたよ。「何になる」「はい、特攻隊になります!」なんて。だって、そう教えられるんですもの。
お二人とも芸術関係に進まれたというのは、やはりお父さんもお好きだったんですか?
(透)
そう、親父も祖父も。だから立派な絵が残ってますよ。
(千秋)
おじいちゃんは絵を描くんです。とっても上手で、すばらしい絵を描く人でした。
(透)
親父は、楯岡出身の昔の俳人・一具の研究をしていました。一具全集の出版もしました。
(千秋)
本当は学者なんですね、実際はね。昔は、学者なんて仕事がないし、田舎にいて長男だからやっぱり家を継がなくちゃいけない。それに戦後は、田んぼも何も全部取られちゃったから、どうやって食べたらいいか分からない。それで、先生をしていましたね。
(透)
勉強してましたから、本当の大学とか高校の先生よりもよっぽど教養がありました。昔は学校の先生が少ないから、それで頼まれたんでしょうね。
(千秋)
歌舞伎は、ものすごく造詣が深いですよ。
(透)
この間、家を壊す時に、それこそ戦前からの歌舞伎のパンフレットが山ほどありました。もうそれまでとっていたら大変だから、半分くらい、誰かが持っていったんですよ。
(千秋)
親戚の家で、楯岡座という、昔の芝居小屋を持っていたんですよね。僕らが子どもの時もまだありましたけど、大事な役者はみんな家に来て泊まっていきました。
(透)
それから菊五郎一座ね、戦後、飯が食えなくて来ていたんじゃないですか。
もう子どもの時から一流とふれあう機会があったんですね。
(千秋)
姉は日本舞踊の花柳流ですけど、東京の花柳寿輔さんが天童に疎開していたから、家のお蔵に舞台をつくって、家を楯岡の舞踊教室にして、そこでお稽古していましたね。
(透)
だから姉も若くして20歳前に名取になったんですよ。寿輔さんも、寿輔さんの高弟なんかも疎開していましたから。花柳寿々音(すずね)というのかな、寿輔さんの寿(じゅ・ことぶき)・音(おと)が姉の名取だったかな。
親父は、昔は地主ということで、東京の國學院大学に行っても歌舞伎の研究とかしていました。祖父の絵とか書もいっぱい残っていて、村山市にも350点だったか寄付しました。
千秋さんが音楽の方向に進んだ時、お父さんはどうでしたか?
(透)
まずは、芸術なんてお金にならない。自分の親父が絵描きで、いろんなことに手を出して、赤紙を貼られてみな持っていかれたとか、そういうことばっかりで全然お金にならないのを見ていましたし、自分もお金にもならない。この長男こそは家を助けてくれる救い主なのに、何を血迷ったか、音楽とか芸事のほうにいくなんて、まかりならんということも頭の中にあったと思うんですよね。
この家を継がなきゃいけない。そういうことがあるから、2人で喧嘩はしていましたね。
喧嘩というか、親父は頑として何も援助しませんでした。
(千秋)
どちらも受け入れませんでしたし…。
(透)
だから僕は、一刻も早く大学を出て稼げるようになりたいと、それだけ本当に思っていました。奨学金をもらい、アルバイトをして、ほとんど家からお金をもらわないで卒業して、卒業すると同時にすぐ働いて金を稼げるようにというか。まぁ、好きな道でもあったけれどもね。
そういう意味では長兄というのは、親父は自分の息子の長男には特に厳しかったのかもしれないですね。
(千秋)
親父は長男に期待していたんですね。それが裏切られたと思ったんでしょうね。
(透)
でも、本当は嬉しいんですよ、音楽をやるって。本当は嬉しいけれども、そこは自分が曲げられない。親父としての権威の表われじゃないですかね、
(千秋)
親父自身はカルテットだとかカルーソーだとか、高価なレコードを買ってきてはそれを聴いていながら、息子が音楽をやると言ったらダメで、「音楽の先生ならいい」と言ったんですけど。
(透)
そう、先生ならいいって。
(千秋)
だけど喧嘩になってしまって、親父と取っ組み合いの喧嘩したことあるんですよ。本当に悪いことしましたね。僕が子どもの時は親父のほうが大きかったけど、だんだん成長して高校生になるとね、親父より僕の背が高くなるでしょ。
一回だけ、掴み合いしたんです、知らないでしょうけど。誰にも言わないから、ここだけの話だから。それっきり、もう、とにかく「やる!」と言いました。
最後の最後まで、「いい」とは言ってくれなかったですね。でも、認めてはくれていたような気がします。
(透)
認めていたけれども、それは親父にしたら死んでも言えない。「いい」とは言えないんですよ。
(千秋)
そうそう。でも、東京で指揮者をやっていた時には、「田舎には帰ってくるな」って言ったんですよね。「山形に帰ってきても何もならないよ。だから、東京でそのままやっていろ」とは言ったんです。
そのほうが親父としては良かったのかもしれません。山形に来ても、もし失敗したら、また恥の上塗りになるんじゃないか、それなら今のままのほうがずっといいと、親父は思ったんじゃないでしょうか。「帰って来てもダメだ、交響楽団なんて山形じゃ絶対成功しない、絶対に誰も金を出してくれない」と。
確かにそうかなと思いましたが、さっき言ったように、考えてみたら僕にはそれしか道はないんですね。山形に交響楽団がないならつくる、それを自分でやりたいですものね。
(透)
昔、家にピアノがなかった時、兄貴は高校生の頃、尾花沢の母の実家まで行ってオルガンを借りて弾いていました。雪の中、尾花沢まで行ったんですよ!
(千秋)
そうそう。ピアノは夜は楯岡小学校でも弾いたし、3か所くらいピアノを借りに行きました。楯岡小学校のピアノはベヒシュタインでしたね。
透さんが映画監督を目指されたのは、どういうきっかけなんですか?
(透)
子どもの頃、村川家一族でつくった楯岡座という劇場があって、映画もやるわけですよ。
そこで観た映画が原点なんですけれども。
その前に、家に蓄音機があって、シューベルトだとかモーツァルトの子守唄を聴かせられていたんです。あと、誰が買ってきてくれたのか、おもちゃの幻灯機がありました。レコードをかけて、幻灯機にフィルムをかけて、部屋を暗くして敷布をスクリーンがわりに広げて映すんですよ。映像と音楽とまるで合わないんですけど、映画のような雰囲気になって、もう魔物のように見えたわけです、僕には。虜になったんですよ。
楯岡座にはタダで入れたから、よく潜り込んで映画を観ていました。そのうちに「僕はいつか、この不思議な世界をつくるほうになる」と思うようになったんですね。
(千秋)
子どもの時のその経験が、全て今につながっている、原点だね、原体験。
(透)
高校は兄貴と同じ山形南高に入ったんですけれども、その頃は音楽に傾倒していて、クラリネットを吹いたりサックスもやったりしていました。でも、やっぱり映画が忘れられなくて、子どもの頃の夢をずっと思い続けて、それを実現したんです。
そうして自分で稼げるようになった頃、兄も一生懸命に山響を立ち上げる時で、「何とか2年間だけでいいから手伝ってくれないか!」ということになったんですね。それで、東京で映画監督をやっていたのをいったん辞めて、「よし、2年間だけ手伝う」と言って山形に来たんですよ。
(千秋)
山響の第1回定期演奏会の時ですね。
(透)
七日町にあった県民会館の大ホールで第1回定期演奏会をやった時、俺は約1700席のうち700枚のチケットを一人で売ったんですから、本当に記録的だと思うんですよ。「五南会」という山形南高5回生の会をつくって、同級生たちに「お前のノルマはこれ」と言ってチケットを渡してお金を集めたりしました。それでオーケストラの旅費とかを工面して、本当に大変だったんですよ。
(千秋)
ちょうど透の自宅の隣が初代山響事務局長の鈴木裕史君のおじいちゃんで、鈴木吉三郎先生といったんですよ。
(透)
僕の嫁の実家が山正鋳造という鋳物屋さんで、義父が人間国宝の高橋敬典さんなんです。
それで、僕が跡取りということになるわけで、近所の鋳物屋の人たちにもチケットを買ってもらったりしましたね。
青年会議所にも入って、文化部長ということに一応祭り上げられて、いかに山形に音楽文化が必要かということをあちこちで話したんですよ。その時に、服部敬雄さんの息子の服部利康さんにも会って…。彼も山形南高だったんです。
(千秋)
僕らの3回下でした。
(透)
そんなツテを頼って、いろいろなところからお金を集めたんです。
服部敬雄さんも、最初はけんもほろろだったんですよ。でも、10万円出してくれました。
(透)
第1回の定期演奏会の時は本当に成功でしたよ。ただ、その時、僕の苗字は「高橋」なので、そういうことを誰も知らないけれども。
それから学校回りをしている時もバスがなくて、山正鋳造のバスを借りましたね。
(千秋)
そのバスを僕が運転して。そのために教習所に通って、大型バスの免許を取って、指揮者自ら楽団員を連れて行ったんです。
でも、ある時、七日町の交差点のところでバスを止めて、ちょっとしたら「先生、後ろ、後ろ、後ろ」と言うから何だと思ったら、ブレーキを踏んでないというわけです。「ブレーキ! ブレーキ!」と。それ以来、楽団員が「先生の運転は、おっかなくてダメだ」と事務局で大問題になって、運転手を雇うことになりました。ただ、その費用はどうするか…と。
最初は何もないから、自分で指揮もしながら、荷物運びもやりもしながら運転もしながら、全部やりましたね。
(透)
そうそう。それは大変だったんですよ、本当に。それで、青年会議所でバスを買ってくれるように段取りをして、それから僕は東京に帰って、監督業に戻ったんですけども、その間の2年間というブランクは大きかったですね。やっぱりみんな後から来た人たちが追い抜いて行って。
その時、悔しかったけれど、今までの分を取り返そうと思って、もう寝る間も惜しんで馬車馬のように働いた、今の3倍くらい働いていましたから。
子どもの頃から独立心はありましね。三男坊の末っ子というのは一番かわいそうなんですよ。それは運命としてね、またこれも面白い。時としてものすごく得することもあるけれども。
(千秋)
ものすごく得だと思いますよ。自由にできるんだから。自由こそ最高ですよ。
(透)
その部分に関しては、本当にそうなんですよ。兄とか姉には目が行くけど、僕のほうまで目が届かないから。そういう意味では自由に伸び伸びと育ちましたね。
その代わり、僕も親からお金をもらったことがないんです。義務教育のお金は出してくれたけれども、中学3年生くらいから町のほうで特別に出してくれる奨学金をもらって、もちろん高校も大学も。大学に入るとすぐにアルバイトをして。それで親父に、初月給からずうっと親父が死ぬまでお金を送り続けていました。
まさにハングリー精神ですね。
(透)
そう、ハングリー精神ですね。浅はかなようだけど、やっぱり人間、稼いでナンボというのは、ある一面は合っているんですよ。芸術であろうと何だろうと、稼げる人は稼げるんだから。だから、そういうふうにならないといかんと思いました。
兄もね、偉いとは思うんですよ、本当に一人で山響をやってきて。しかし、やはり金がないというのは情けないですね。
(千秋)
いやいや、僕は。やれる分だけやってきただけ。幸運だったんですよ。
最後に千秋さんに、将来の担い手として子どもたちを育成しているヴァイオリンの「キラキラ会」について一言、お願いします。
(透)
兄には、子どもこそ宝であり全ての「もと」だという信念が根底にあるんですね。最も感激したのは、「大人からはお金は取っても結構。でも、これから僕たちを支えてくれる子どもからお金を取るなんてことは考えられない」と、昔、僕に言ったんです。
(千秋)
それで、指導は無料だったんですね。
(透)
それがね、俺はショックを受けたというか。「もと」になる子どもたちの才能こそ、伸ばしてやらなきゃいけないと。それにものすごく感激して、今日に至ってるというのが本当ですね。
(千秋)
子どもたちが、自分が何をしたいのか分からないと大変ですけど。何をしたいのか、分かるまでが大変ですね。
何をしたいのかが早くに分かる子と、大人になってから分かる人といるのでしょうが、お2人はどちらかというと、早いうちに分かったんですね。
(千秋)
割と早いうちに決めましたね。
(透)
思い続けるとか、それがなかなか難しいですけれども、思い続けている自分をもう1回、思い出す、思い返すことですよ。いつでも人間は立ち直れますから。だから、何をやりたいか言い続けてくださいと。よく原点にかえれと言いますが、言い続けましょう、何をやりたいか。我々も、必ずやる、忘れないで。
(千秋)
そうだね。
根底にあるのは、やっぱり好きなものに出会えたことですね。
(透)
そうそう、そこですね。そして、やるからには生涯かけてやると。僕らの助監督にも、それを言うんですけれどね。自分でいったん、そういうふうに決めたわけでしょ。それだったら、「生涯かける気持ちでそれやりなさいよ」と。「その代わり、後戻りは絶対できないよ」と。
それに、できないならできないなりに道は必ず開けるし、別なところにいったら、またそれと同じことだから、それで開けるかもしれないから…と言っています。
やっぱり人生に無駄なことは何もないですね。
(千秋)
ないですね。
(透)
ない!
(千秋)
「キラキラ会」でヴァイオリンをやって高校まで続けて、長い時間、一生懸命にやってきたら、必ず何か、その人の身になってるはずですよ、何かに助けられるから。
(了)
収録日:2013年6月25日 収録場所:キラキラ会練習スタジオ インタビュー:キラキラ会有志 公開日:2025年5月20日