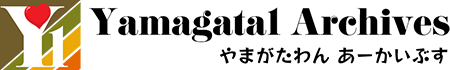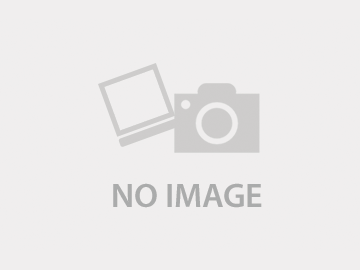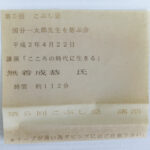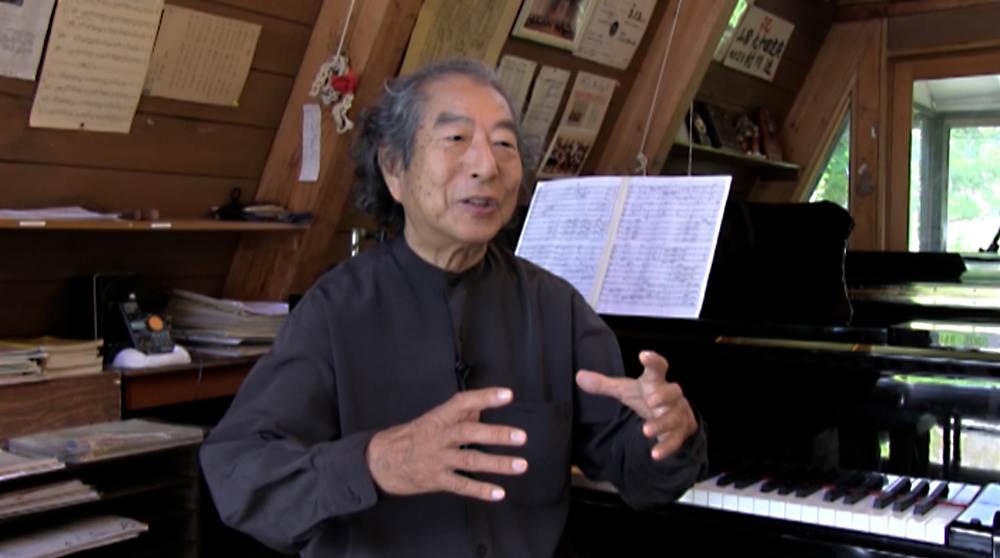AI音声による解説
AI音声による解説は、横尾量助さんの戦時中の子供時代を振り返った回想を扱っています。特に、学童疎開の受け入れ、徴兵検査、軍事優先の暮らし、神町飛行場の襲撃、そして戦後の教育の変化について詳述しています。
開戦から戦後へ~戦争とともにあった少年時代
横尾量助さん
(よこお りょうすけ)
(東根市)
収録日:2021年10月28日
公開日:2025年8月12日

戦中の学校生活
私は昭和9年の4月3日に東根町の八日町、現在の東根市本町の生まれです。
昭和16年4月、尋常小学校から国民学校に変わった年に東根国民学校に入学しました。
今の東根小学校です。
大東亜戦争が始まったのは、その昭和16年の12月8日、東根国民学校の1年生の時でした。寒い時期でしたけれども、その日、学校に行くと、全校生徒が学年ごとに整列して若宮八幡神社に行き、日本軍の必勝と武運長久を祈りました。長靴なんてない時代でしたから、つま掛けの草鞋とか藁で編んだ深靴を履いて、みんなで行きました。
「戦(いくさ)始まったからアメリカやっつけろ!」というような気持ちで、必ず勝つと信じていましたし、真珠湾攻撃とか山本五十六とか、子どもながらに本当に感激して聞いておりました。
学校では、「ご飯いっぱい食て、早ぐおっきぐなて、お国のために働らがんなね~」というふうに教えられていましたので、私も航空兵になりたいと夢見ていました。当時は、男子学生はみんな少年航空兵や陸軍少年兵を目指して、体力づくりに励んだものです。戦争に勝つためには当然のことだと思っていました。
憧れの柴田航空兵
3年生の秋頃、我々の憧れ・柴田航空兵の飛行機が学校にやって来ました。柴田航空兵は三日町の出身で、同じ学校の卒業生でした。
その柴田航空兵が操縦する飛行機が、学校の上空を旋回するというので、全校生が日の丸の小旗を持って、校庭に「シバタ」の人文字をつくって待っていました。長い時間、待ったような気がします。
やがて南の空に飛行機が現れ、グルグルと旋回すると、全員「万歳!万歳!万歳!…」と大声で日の丸の小旗を振りました。
飛行機が見えなくなると、友だちと「顔が見えっけ」「大欅の枝にぶつかりそうだっけ」などと話し、「自分もご飯いっぱい食って、一日も早く大人になって、飛行兵になってアメリカをやっつけらんなね」と強い気持ちが湧いてきました。当時は、日本は絶対に勝つと思っていましたし、そういう教育を受けていました。
子どもも勤労奉仕
戦中とはいえ、3年生頃までは学校生活も楽しいことがあったような気がします。しかし4年生5年生になると戦争の色が濃くなり、勉強どころではなくなりました。
私たちはよく、出征兵の留守農家へ行かされました。兵隊に行って働き手のいなくなった農家の手伝いです。豆を蒔いたり、草取りをしたりしました。
ほかにも、学校の体操場で養蚕、おごさま(お蚕さま)を飼ったり、酒石酸をとるためのワイン用のぶどうの葉を取ったり、イナゴを捕まえたり、落穂拾い、ドングリ拾い、ツブ取り、山の杉起こし、桑の木の皮剥き、鉄屑回収など、いろいろなことをさせられて授業はほとんどありませんでした。
ドングリは粉にして、代用食のパンをつくったのです。
桑の木の皮は、先生たちから「お前だ、一所懸命したなで、服もらういなだぞ」と言われていました。何キロ出すと、何がもらえたかということまでは知りませんが…。
東京からの学童疎開
日増しに戦争が激しくなった昭和19年、4年生の秋、空襲を避けるために東京から同じ学年の児童数十名がやってきました。2クラスくらいだから、男女あわせて60人から70人ほどだったでしょうか。学童疎開で、東根温泉の「鶴の湯」で集団生活をしていました。
同じ4年生といっても、学校で一緒に遊んだり勉強した記憶は、私にはありません。私たちは戦時中でも元気いっぱいで遊んでいましたが、疎開してきた人たちは体操場の隅にかたまっており、私たちとの交友はなかったと記憶しています。
親元を離れて、知らない土地での生活で寂しかったのでしょう。今になって、仲良く話しかければ良かったと思います。
ただ、落穂拾いはしました。先生から「集団疎開してきた人さ、落穂拾いしたので餅(もづ)ついで食べさせるんだ。んだがら一所懸命拾てこい」と言われて、みんなで落穂を拾いました。
徴兵検査と赤紙
召集令状、俗に赤紙といわれていましたが、赤紙は私の父にも来ました。
最初の頃は、赤紙が来て出征する方がいると、出征軍人を送る旗を立ててみんなで駅までお見送りしました。
それから戦死した方は、みんなで東根駅に行ってお迎えして、昭和12年の支那事変のあたりまでは、東根町の町葬のようなことまでやってくれたのです。父親は陸軍歩兵少尉で東根在郷軍人分会長だったので、遺骨が来ると黒い腕章をつけて駅まで迎えに行きました。
後になってからは、ただ小さな骨箱だけ届いて、中に入っていたのは名前の書かれた紙だけだったとか、いろいろ聞いていますけれども。
私はまだ子どもだったので受けていませんが、男子は20歳になると全員、徴兵検査がありました。東根国民学校に集められて、板とかで仕切られた体操場で、丸っ裸になって検査されました。
甲種合格は五体満足どころか全てが健康で、身長体重も標準以上の身体頑健な方しかなれません。近眼でも甲種にならなかったですから。だから「俺は甲種合格だぞ~」「おらいの息子、甲種合格だ」と、それは威張ったもんです。
一方で乙種や丙種の人は、「嫁ももらえない」とか非国民的な目で見られたと思います。
軍事優先の暮らし
戦時中は、電力不足でよく停電がありました。東根国民学校の大欅のところにあった体操場は軍需工場(こうば)になっていて、旋盤がいっぱいありました。軍需工場優先で、こういうところで電力を使ったから、家庭まで電力が回ってこなかったのでしょう。日中は電気を止められました。
父親が東根在郷軍人分会長だったからなのかどうか分かりませんが、私の家には大きい地図がありました。「どごそごで軍艦沈めたど」と聞くと、その場所にシールを貼っていくのです。次々とアメリカをやっつけていく、それが楽しかったですね。
けれど、そういう時期も1年ぐらいだったか、だんだん攻めらてきて、シールを貼ることもなくなりました。
私の家でも、裏門のところと庭のほうに防空壕を2か所、掘りました。万一、空襲があった時、家族全員が同じ防空壕に入ると、みんな一緒に死んでしまうからです。
大きいほうの防空壕には、うちの貸家の人たちも入りました。蚊がいっぱいいて、蚊に刺されて小さい子どもが泣き出すと、「大っきい声出すど、アメリカさ聞こえっどー」「子どもば泣がせんな~」と、そんな声がしました。でも、蚊取り線香もないし、団扇でパタパタ仰ぐくらいしかできず大変でした。
家が予科練生の宿舎に
昭和20年の春頃、神町の海軍航空隊から私の家の一部が接収されました。上段の間と二の間の2部屋には山本五十六と一緒に攻撃したという海軍兵士の家族3人が暮らし、中間(なかま)と勝手のほうには予科練生20人ほどが住まいしていました。
父親は山形の連隊に召集されていましたので、私たち家族は仏壇もみなお蔵の蔵座敷に移して、私と母親と姉2人の4人で蔵座敷と台所で生活しました。
昭和17年に神町に「神町海軍航空隊」が設置されて、予科練生の操縦教育の基地になりました。そこで飛行機の練習をやって操縦を覚えて、特攻隊になって行くのです。家にいた予科練生は九州の方がほとんどで、19、20歳くらいの人たちでした。
どうして私の家に予科練生がいたかというと、14間(けん)の大きなお蔵があったからです。飛行場が襲撃される危険があるため、こうした個人の蔵や地域の郷蔵(ごうぐら)に軍服や軍靴、航空食などの食料といった物資を疎開させていました。飛行場が爆撃された場合の物資確保のためだったと聞いております。
予科練生は、その蔵を警備する任務のため、私の家に駐留していたわけです。家の門の前にも歩哨が交替で立っていました。
郷蔵(ごうぐら)というのは、飢饉などに備えて部落の人が米や種籾を溜めておくところです。いつの時代からあったのか分かりませんが、光専寺沼のところに2つ、新町などにも建っていましたし、昔から数か所にありました。
それから、予科練生が休みの日に家庭に宿泊させる制度がありました。私が4年生5年生の頃なので、予科練生は私を弟のように「坊や、坊や」と言って遊んでくれました。
当時は食べ物が不足していましたが、近くにモモヤ食堂というのがあって、なぜか「みつ豆」を売っていました。その店に、家に泊まった予科練生が〝ちゃんこぐ〟(肩車)して連れて行ってくれて、「みつ豆」を食べさせてくれました。確かに小豆が入っていて、甘かった…あの「みつ豆」は忘れられません。
その予科練生は大塚さんという方でしたが、終戦から10年くらい経った頃だったか、家を訪ねて来たことがあります。ちゃんと背広を着て、最初はどなたか分かりませんでしたが懐かしかったですね。神町から家まで歩いて来たそうで、「思い出に歩いて来ました。変わりましたね」と言っていました。
落下傘の降下騒動
昭和20年6月の初め、栗の花が咲く頃のことです。「沼沢方面にアメリカ軍の落下傘が落ちた」という騒動がありました。
誰も落ちたところを見たわけではありませんが、これは陸上戦の前触れか、偵察に一人降りて来たのではないか、大変なことになった…と大騒ぎです。それで屈強な若い男衆が10人くらい、竹槍とか火事の時に使うトビ(鳶口)とか思い思いの武器を持って、一日町(ひといちまち)にあった消防ポンプの自動車と土建屋のトラックに乗り込んで「アメリカば、やっつけらんなね。捕虜にしてくる」と勇んで出かけました。それを、「頑張てこいな~」と、みんなで万歳、万歳と見送りました。
ところが行ってみると、落下傘と思った白い物体は、真っ白い花に覆われた栗の大木。ふわふわした真っ白い花が満開の木を、遠くから落下傘が落ちたと勘違いしたのです。男衆が「いや~、栗の花咲いっだんだっけ」と帰ってきて、まるで漫画のような話でした。
風防窓枠の落下事件
神町飛行場が襲撃される少し前の昭和20年7月頃、アメリカ艦載機の風防窓枠が落下するという事件がありました。
この頃には、グラマン戦闘機とかB29爆撃機とか、東根上空にもよく来るようになって、電波妨害のために空から銀紙を撒くことがありました。
その日もグラマン戦闘機が飛んで来て、なんと飛行機から風防の窓枠が外れて、堂の前あたりに落下したのです。それを見た周辺の住民が「何が落っできた~」「んだら、予科練さ教えろ~」というので、光専寺沼のところに立っていた歩哨に知らせました。そして、風防窓枠は戦利品として私の家に運び込まれました。
終戦になり、風防窓枠が残されて、「これは戦利品だから、アメリカの駐留軍が来て見つかったら大変だ。殺されるかもしれない」と近所の人に言われました。今考えれば、それほど重要なものでも、盗んだものでもないわけですから問題なかったのでしょうが、その時は怖くなって、しばらくの間、蔵の奥に隠しておりました。
この窓の風防ガラスは厚さが7、8ミリあって、燃えたんです。それで、革靴で割って小さくして、停電した時にそれを燃やして灯りの代わりに使った覚えがあります。だいぶ湯気が出ましたけれども。アルミ部分の枠は、少し落ち着いてから処分して、事なきを得ました。
神町飛行場を中心に襲撃
昭和20年8月9日の早朝、アメリカの艦載機グラマン戦闘機による機銃掃射がありました。東の空から突然、20数機の戦闘機が飛んで来たのです。
警戒警報や空襲警報のサイレンは学校の屋根の上で鳴るのですが、まだ空襲警報が鳴る前だったので、縁側から空を見上げて私は日本の飛行機だと思い、「日本にこんなにいっぱい飛行機があるんだ~。これでは日本は必ず勝つな」と思いました。
その瞬間、頭の上でババババーッと機銃掃射が始まったのです。ものすごい音がして「わぁ~アメリカだ! 殺される~」。もうビックリして恐ろしくて、裏の防空壕に行けずに蔵座敷に隠れました。この時、初めて死の恐怖を感じました。
楯岡の女学校に汽車で通っていた姉は、家を出たばかりで戦闘機が来たので、土手に伏せて隠れたと言っていました。
神町の駅前は焼夷弾を落とされて火事になり、ほかにもそっちこっちが焼けました。
神町飛行場には、地域の人たちがお金を寄付してつくった戦闘機があり、若木山(おさなぎやま)には高射砲があり、敵機が来ても安心と聞いていたのに、この時は何の反撃もなく、やられっぱなし。子ども心に不思議に思ったものです。
戦後はアメリカ軍が駐留
終戦の日、昭和20年8月15日、天皇陛下の玉音放送を聞きました。5年生の時です。よく理解できませんでしたが、親から「日本、負げだんど」と教えられました。
戦争が終わると、アメリカ軍が旧海軍神町飛行場キャンプに駐留して、町でアメリカ兵を見かけるようになりました。鉄砲を持っていて、下手なことをすると空に向かってバーンと撃つので、しばらくは怖かったです。
大高根村(現村山市)にはアメリカ軍の実弾射撃演習場がつくられて、朝晩、大砲を乗せたトラックが旧国道を通りました。ここは軍事道路というので、早くからアスファルトになったのです。
日中は砲撃演習で、バーンバーンと大砲を撃つ音がここまで響いて、今にようにアルミサッシの窓ではなく障子一枚ですから、家がガタガタと揺れました。
警察も、戦後は今のような警察制度ではなく、東根自治警察というのがありました。家の裏の竹藪から留置所が見え、電気がつくと「あれ、今日、誰か留置所にいだ」と分かったものです。
終戦でガラリと変わった学校教育
5年生で終戦を迎え、それからは「お国のためになる生徒」をつくることが目的だった国民学校の教育がガラリと変わりました。今まで習っていた教科書は「何ページの何行目から何行目まで、墨を塗って消せ」と、軍国主義に関わるところを毎日、墨塗りするのが日課でした。
その後に渡された新しい教科書は紙のままで、それを自分で切って本のように綴じました。
学校制度も昭和22年から「六・三・三制」、小学校6年・中学校3年・高校3年に変わります。昭和9年生まれの私たちは、この「六・三・三制」の影響をまともに受けた学年でした。
私は国民学校を卒業したら山形の中学に入りたいと思っていたので、6年生の時には友だち20人くらいが家に来て、一緒に受験勉強をしていました。それまで戦闘帽しか被ったことがなかったので、中学の白線をした帽子が憧れだったのです。それが、全生徒が新制中学に入ることになり、複雑な気持ちでした。
昭和22年の3月に国民学校を卒業しましたが、東根中学校の校舎がありません。小学校の北校舎を区切ってできた校舎と、旋盤などがあった体操場を元に戻して校舎にすることになり、その作業が終わった5月3日、1か月遅れで東根中学校の第1回生として入学しました。
ようやく中学生活が始まったものの、先生が足りず、日本刀を下げた先生もいました。
その後、大林地区に新しい校舎を建てることになり、私たち生徒も河原から石を運んだり、町有林の「奥山野」で伐採した木を引っ張ってきたり手伝いました。
昭和24年11月に校舎の一部が完成すると、それぞれ椅子や風呂敷に包んだ荷物を持って引っ越しました。
昭和25年、高校入学の時は学区制が施行されていて、北郡では普通高校は楯岡高校と大石田高校の2校以外、受験できませんでした。それで、私は楯岡高校の普通科に入りました。戦争が終わっても物資は不足していて、私は、高校まで父親の軍服を着ていて、卒業写真も軍服姿で写っています。
子どもたちのために~「横尾文庫」
昭和28年、私は高校を卒業すると山形銀行の前身の両羽銀行に入りました。入行後は県内各地や仙台など13か所の支店に勤務し、40年間勤めて山形銀行の東山形支店長を最後に退職しました。その後、企業の常務、東根市農協の監事を務め、今は東根ロータリークラブで奉仕活動に携わっています。
私が国民学校の頃、担任の三浦先生が光専寺の沼のあたりで本を読んで聞かせてくれました。当時、東根には本屋がありませんでしたし、戦争の最中ですから読みたい本を自由に読むこともできませんでした。そうした体験があったので、たまたまある会合で「学校は図書の予算が少ない」という話を聞き、「少しお手伝いするか…」と東根小学校に図書費10万円を寄贈したのです。平成6年、ちょうど孫が生まれた年でした。
その時、当時の校長先生が「横尾文庫」と名付けてくれたものですから、それから毎年、贈るようになり、今日まで続いてきました。これからも、子どもたちが好きな本をたくさん読めるよう、陰ながら力になりたいと思っています。
(了)
収録日:2021年10月28日 聞き手:たなかゆうこ 収録:伊勢 博